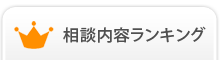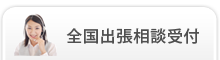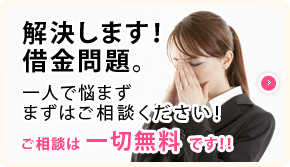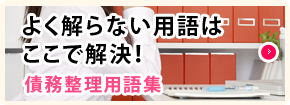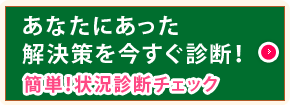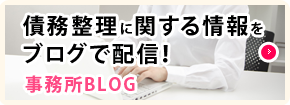近藤邦夫司法書士事務所 トップページ » 債務整理用語集 » 債務整理用語集の解説(さ行)
債権者
特定の人(債務者)に対して、一定の給付を請求することができる人。資金を借り入れている金融機関や商品を納入している業者など。
催告の抗弁権
債権者(金銭の貸し手)から保証人が「貸した金を返してほしい」などの請求を受けたとき、自分よりまず債務者に請求してほしいと主張できる権利。債権者が主債務者(借りた本人)への請求に先立って保証人に請求をしてきたときに、「まずは主債務者に請求してください」と主張できる権利。この権利は保証人にはあるが、連帯保証人にはない。
債務者
特定の人(債権者)に対して、一定の給付義務を負う人。
債務名義
強制執行をする場合に、その請求権があることを証明する、執行力を付与された公的文書。判決や公正証書・支払督促などがあり、いずれも公証人役場や裁判所などの公的機関によって債権の存在を証明する文書であることから、債権者の債権回収の確実性が非常に高まる。
差押え
債務者が勝手に自分の財産等を処分し、債権が回収できなくなることを防ぐために公権力によってその処分を禁止する財産保全の方法。ただし、どんな財産でも差押えができるわけではなく、たとえば日常生活に必要な家財等は差押ができないし、給料については、手取額の4分の3は差押えが禁止されている。差押えの申立ては、債務者の住所地を管轄する地方裁判所にする。
サラ金
サラリーマン金融の略称だが、現在は消費者金融との呼称が定着している。主に無担保・無保証で一般の個人消費者へノンバンクの融資を行う業者のこと。
時効
ある状態が一定期間続いたら、その状態に合わせて法律関係に変更を生じさせる制度。権利がなくなってしまう「消滅時効」と、逆に権利を得る「取得時効」とがある。
たとえば、貸金業者などからお金を借りた場合、その借金は5年で時効となり、もともと借りていなかったことになる。ただし時間だけが経過すればよいわけではなく、請求をずっと受けていないことや時効が完成後に援用(時効の利益を受けることを主張)する必要があるので、簡単に時効が成立するということではない。
残高スライド方式
リボルビング返済方式の一種。借入残高によって、毎月の返済額が変動する返済方法のこと。借金問題のご相談は、何回でも無料です。
実質年率
借りたお金に対して、一年間にどれだけの金額の利息が付くかという、年利のこと。消費者金融会社では、借りた日数分に利息がかかる日割計算をする場合がほとんど。
出資法
「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」のことで、貸金業者の金利の上限や違反した場合の罰則などを定めている。貸金業者の上限金利については、利息制限法(元本10万円未満は上限20%、元本10万円以上100万円未満は上限18%、元本100万円以上は上限15%)と、出資法(上限29.20%)に定めがある。多くの貸金業者が罰則のない利息制限法の上限を超え、罰則がある出資法の上限を超えない範囲で貸付を行っている。
消費者金融
主に個人消費者への融資業務を行う金融業者を指す。一般的に無担保・無保証で借りることができ、審査から融資までの期間が短いのが特徴。ただし利息制限法を超えるグレーゾーン金利(高金利)で融資をしている業者が多い。
信販会社
無担保で「個人の信用」を基礎に、月賦など後払いで商品を渡す販売方法を提供する会社のこと。収入等の事情によっては契約できない(カードを作れない)場合もある。
商品の代金を消費者に代わって販売会社に立替え払いをし、のちに消費者から後払いを受けることによってそれを回収する会社。割賦販売を斡旋するクレジット会社のこと。