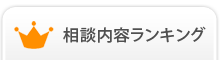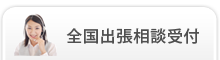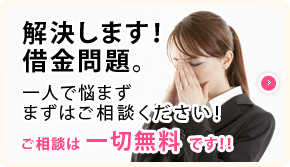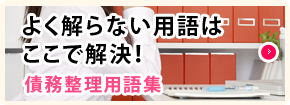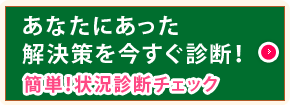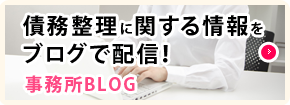近藤邦夫司法書士事務所 トップページ » 債務整理用語集 » 債務整理用語集の解説(か行)
ガイドライン
貸金業規正法の考え方をより明確に示した金融庁の指針。貸金業者に対して、具体的な禁止行為(例:暴力的な態度をとること・法律上支払義務のない人への支払請求をすること・勤務先を訪問して債務者や保証人を困惑させたりすること等)や取引履歴の開示義務について示している。
貸金業規制法
過剰融資
カード会社や消費者金融などが、融資の申込をした人の返済能力を超えた金額を貸し出すこと。過剰融資がされると、債務者は手持ちのお金では借金が返済できなくなるため別の金融機関から借金をするといった、自転車操業になりやすい。各社の利息回収を目的とした高額融資やその勧誘行為は、過剰融資として貸金業規制法により禁止されている。
過払い
消費者金融など高金利が設定されている業者との取引の中で、自分で借り入れた元金と、その法定利息を返済し終わっているにもかかわらず、法律上の義務なく返済してしまった金額のこと、またはその状態を指す。
借入限度額(与信限度額)
借入をしようとする人の経済的な信用に応じて決められる融資などの限度枠のこと。新規の融資申込者については、年齢や年収・勤務先からその信用力を審査して、最初の融資枠を決める(初期与信)。その後、既存顧客の信用力を管理する(与信管理する)ことにより、信用力を見直していくことを途上与信といい、途上与信で信用力が高まれば融資枠を広げるなどの判断がなされる。
仮差押え
債務者が勝手に財産等を処分し、債権が回収できなくなることを防ぐために国家権力によってその処分を禁止する財産保全の方法。債権回収を目的とした強制執行を行うためには、判決その他の「債務名義」という公的な証明が必要になる。しかし、債務名義を入手するまでに債務者が財産を処分してしまえば、債務名義をもらっても債権を回収することはできない。そこで、仮差押によって債務者の財産を暫定的に確保するという方法をとる。
元金
利息を含まない借入金額のこと。消費者信用における債権は、元本と利息を併せたものをいう場合がほとんど。元本とは、「与信額」と同じ意味で使われる場合もある。実際に借金の返済をする時には元金と「利息(実質年率)」のパーセンテージを掛けた金額の総額である。
元金均等返済
元金を均等割にして返済する方法をいう。元利均等返済に比べて元金の減少が早いため支払をしていくうちに毎月の返済額が少なくなる、元利均等返済よりも総支払利息が少なく総返済額も少なくて済むというメリットがある一方、最初の負担額が大きくなるというデメリットも。
期限の利益
決められた期限までは、お金を返す必要がない、返済を請求されないといった、期限が到来していないことで債務者が受ける利益のこと。ほとんどの金銭消費貸借契約には「期限の利益の喪失」の条項が盛り込まれている。たとえば、決められた期限までに返済が間に合わない場合、期限の利益がなくなったものとし(期限の利益喪失)、借金の残額を一括で支払うこと、などといった特約である。
求償権
他人のために、金銭などの財産を支出した者が、利益を与えた人に対して「財産を返してくれ」と請求できる権利のこと。たとえば、本人の代わりに立替払いをした時や保証人が債務者本人に代位弁済した時などに求償権が発生する。
強制執行
債務不履行などがある債務者に対して、裁判所を通して強制的に債権を回収する手続のこと。(給与差押や不動産競売など)強制執行は国家の力の使って債権を回収することであり、そのためには判決その他の「債務名義」とよばれる公的な証明が必要になる。
金銭消費貸借契約
金融機関からお金を借りる時に交わす契約。
消費貸借契約は、民法で「金銭その他の物を借り受け,後にこれと同種、同等、同量の物を返還する契約」と定められおり、借受物を消費することが可能であり、返還の際にはまったく同じものを返還する必要がない点で賃貸借契約などと異なる。
金銭消費貸借契約が成立するためには、借主が金銭を貸主に返還することを約束し、貸主から金銭その他の代替物を受け取ることが必要であり、「押し貸し」などのように一方的に金銭の提供を受けただけでは成立しない。
公正証書
「公証人」(法務大臣によって任命された公務員)が、当事者の依頼によって作成する公文書のこと。公正証書は、「債務を履行しない場合には、ただちに強制執行を受けても異議のないことを任諾する」という文言(強制執行認諾約款)が入ることも多い。この文言が入っていると債務名義として認められ、債務者が借金の返済をしなければ、公正証書を裁判所に提出することですぐに給与差押などの強制執行が可能になる。