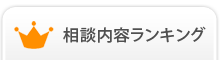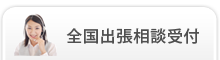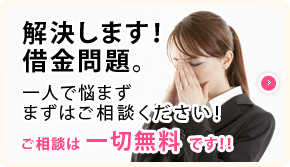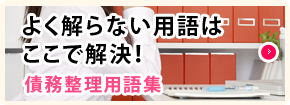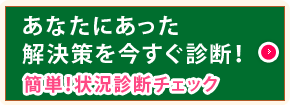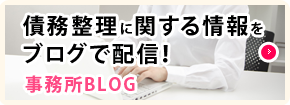近藤邦夫司法書士事務所 トップページ » 債務整理用語集 » 債務整理用語集の解説(は行)
ブラックリスト
個人信用情報機関に登録された長期延滞者や自己破産者、債務整理者などの記録の俗称。ネガティブリストとも呼ばれる。個人信用情報とは、契約内容や返済状況などに関する情報であり、金融会社等が、その人物の返済能力を判断する際の参考資料として利用することが多い。支払の遅れや不払い、破産などのトラブルがある場合には、大体5~7年間の間、事故情報として登録される。この間は新たな借入れは難しくなる。
フリーローン
資金使途が特定されていない、消費者ローンのこと。クレジットカードローンや消費者金融などは、フリーローンの場合が多い。これに対して、車の購入のための自動車ローンや教育ローン、結婚式などを対象としたブライダルローンを目的別ローンという。目的別ローンは使途証明書の提出など審査基準が厳しいかわりに、フリーローンよりも金利が低くなる。
弁済
債務者による債務の給付、あるいは履行のこと。
債権の目的を実現させることであり、借りたお金を返すことも弁済にあたる。
変動型金利
市場金利の上下によって、ローンの返済中に金利が変ってしまう制度のこと。半年ごとに、利息がその時の金利水準にあわせて見直される。ただし、実際の返済の変更は5年間ごとに見直される仕組みになっている(返済額が増えても最大25%以内)。低金利の時代が続けば、それだけ負担を低く抑えることができるが、逆に高金利の時は、返済金額が当初の予定よりも高くなる場合もあり、固定型金利よりも不安定なローンと言える。
法定利率
個別の金銭消費大役契約などにおいて利率を定めなかった時に、適用される金利のこと。民法上は年5%、商法上は年6%とされている。その他、利息制限法では元金の金額によって15%~20%の上限が定められている。